短大のTOPICS(~2012)
ストリートチルドレン支援から学ぶ地域連携の重要さ
2009年12月03日 【 お知らせ|国際コミュニケーション科 】
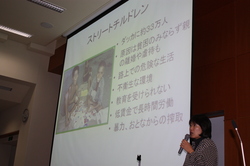
12月3日(木)、東京の国際協力NGO「シャプラニール=市民による海外協力の会」の前ダッカ事務所長藤岡恵美子さんをお招きして特別講義が行われました。
藤岡さんは4年4ヶ月間バングラデシュの首都ダッカに駐在して、今年9月に日本に戻られたばかりです。
バングラデシュはインド同様、急激な経済発展を続けており、都市と農村の経済格差や都市内でも貧富の差が広がっているそうです。しかし、政府の福祉制度は十分とはいえず、依然外国からの援助が貧困層の人々の生存、生きる希望を支えるために必要です。
シャプラニールは1999年から、ダッカに30万人以上いるといわれるストリートチルドレンの支援を地元NGOと協力して実施してきました。安心して寝泊りができ、自分の持ち物を預けることのできるロッカーを備えた「ドロップインセンター」を子どもの保護のために運営し、バスセンターに併設された青空教室での基礎教育をはじめ、生活していく上で必要な知識を教えたり、自立のために技術訓練を提供したりしています。
この10年間の活動が地域に認められ、今では地元住民(大人)がセンターの運営に協力する体制が整ってきています。野菜市場の労働者は野菜や米をセンターに提供してくれるようになり、近くの学校では子どもたちと一緒に交流してくれるようになってきました。貧しい母親たちも米を一握り集めて寄付しているなど、自分や知り合いの子どものことだけではなく、ストリートに生きる子どもたちをも地域の子どもとして面倒をみていく動きが出てきたといいます。
最初の頃は、こうした子どもたちは汚い言葉で罵られることも多くあったといいます。ストリートチルドレンの問題を解決するには、子どもの保護だけではなく周りの大人たちの認識(危険な子ども、厄介な存在)が変わることが必要です。大人たちが地域ぐるみで小さな行動を起こしてくれるようになるまでじっくりと語りかけ、理解を得ていくこともNGOの重要な仕事であるということがわかりました。
私たちの身の回りで、誰がこうした地域ぐるみの取組みを進めているのでしょうか?子どもを地域でどう育てるか、自分たちの地域の問題として考えさせられました。
(武田)
前の記事 | 新着一覧(~2012)に戻る | 次の記事
